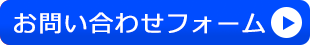目次
福岡県で古物商許可を取得されたい方へ

●警察との打ち合わせ、●申請書作成、●申請書提出、●警察からのヒアリングへの回答(申請時)、●警察からの問い合わせ・確認への回答(審査期間中)、●補正(発生した場合)、●古物商許可証の受け取りまでワンストップでお任せいただけます。
ご依頼時のヒアリング・打ち合わせは、お電話やご面談など、ご希望の方法をお選びいただけますので、お気軽にご相談下さい。
料金
| 古物商許可の申請代行 |
(個人様)申請代行 お支払い総額 55,300円 報酬:36,300円(税込)+19,000円(警察署に納付する手数料) (法人様)申請代行 お支払い総額 65,200円 報酬:46,200円(税込)+19,000円(警察署に納付する手数料) |
|---|---|
| [ 料金の内訳・詳細はこちら ] | |
古物商許可の課題を解決します
- リサイクルショップを始めたいが、古物商許可の手続き方法が分からないので代行してもらいたい。
- 中古車の販売店を開業予定だが、開業準備に専念したいので、申請手続きを代行して欲しい。
- トレーディングカードの販売・買取をしたいので、古物商の手続きを代理で行って欲しい。
- 副業でAmazon等のショップを利用して古物の売買を始めたいので古物商許可を取りたい。平日日中は仕事があり手続き方法も分からないため代行を依頼したい。
- 開店の準備に専念したいので、許可申請の手続きを代行してもらいたい。
- 申請の方法を調べたり、移動の時間をとるのが難しいので手続きを代行してもらいたい。
- 効率よく古物商許可を取得し、できる限りスムーズに営業を開始したい。
- 会社の事業の一環としてメルカリやヤフオクなどのネットショップで商品を仕入れて販売(転売)したいので、古物商許可の申請手続きを代行して欲しい。
この他にも古物商許可について、お客様特有の課題、お悩みがあると思います。まずはお話を聞かせていただきますので、お気軽にお問い合わせ、ご相談ください。
古物商許可・対応地域

地域に密着し、迅速な対応を大切にしておりますので、福岡市およびその周辺地域を古物商の主たる営業所とする申請に限定して、対応させていただいております。(お客様の状況に応じてその他地域も対応できる場合がありますので、お問い合わせ下さい)
下記地域が対応地域となります。(カッコ内は管轄警察署)
| 福岡市中央区 (中央警察署) |
福岡市博多区 (博多警察署) |
福岡市東区 (東警察署) |
| 福岡市南区 (南警察署) |
福岡市早良区 (早良警察署) |
福岡市城南区 (城南警察署) |
| 福岡市西区 (西警察署) |
春日市 (春日警察署) |
大野城市 (春日警察署) |
| 那珂川市 (春日警察署) |
太宰府市 (筑紫野警察署) |
筑紫野市 (筑紫野警察署) |
| 糟屋郡 (粕屋警察署) |
古賀市 (粕屋警察署) |
糸島市 (糸島警察署) |
| 福津市 (宗像警察署) |
宗像市 (宗像警察署) |
理想とするお店実現のために

当事務所に許可の取得を代行いただくことで、店舗戦略、商品戦略などの準備に専念していただくことができます。
古物商許可の取得をお考えの際は、お気軽にお問い合わせ・ご相談ください。
古物と古物商許可

古物とは、分かりやすく言えば「一度使用された中古品」のことです。
ただし、それだけではありません。
一度も使用されていないが買ったり、譲ってもらったもの、あるいは、それらのものに幾分の手入れしたものも古物に含まれます。幾分の手入れとは、物の性質や用途を変化させることなく修理等を行うことです。
このような中古品(古物)の売買、交換、レンタル等を業として行う場合(古物営業)に必ず取得しなければならないのが古物商許可です。許可なく営業すると処罰の対象となります。
簡単に言うと、車の免許を取らないと車を運転できないのと同じように、古物を取り扱うには古物商許可が必要だということです。
また、店舗だけでなく自身のホームページやネットオークションを通じて継続的に中古品を取り扱う場合も古物商許可が必要になります。
「業として行う」とは、中古品を継続的に繰り返して取引する行為のことを言います。ざっくり言えば、利益を得るために中古品の売買などを繰り返し行うことです。
中古品といってイメージしやすいのは、古本、古着、中古家電、中古家具、中古車、骨董品、中古CD・DVDなどでしょうか。
このような中古品の売買等を業として行う場合は、古物商許可を取得することで適法に営業を行うことができるようになるわけです。
なぜ古物商許可が必要なのか?
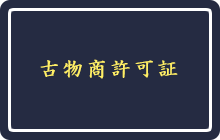
古物営業法の第一条に「この法律は、盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業務について必要な規制等を行い、もつて窃盗その他の犯罪の防止を図り、及びその被害の迅速な回復に資することを目的とする。」とあります。
これを実現するための中核をなす制度が、古物商許可です。
自由な古物売買等を認めてしまうと窃盗や強盗などの犯罪被害品の処分が容易に行われ、犯罪の助長につながる恐れがあります。
簡単に処分できるとなれば、窃盗などにより換金しやすくなり、犯罪へのハードルが低くなってしまい、助長されてしまうんですね。
そこで、許可制することで、警察が古物商を把握し、一定の監視の目があることをもって、犯罪の抑止を図ることになります。ひいては被害の防止にもつながることになります。
例えば、処分することによって足が付くことを恐れ、窃盗などを実行に移す前にやめようといった犯罪抑止力の役目があります。
あるいは、被害品が処分された場合は、警察によって古物商が把握されているわけですから、古物商をあたることで事件解決の手がかりにつながる場合もあります。
このように古物商許可によって、被害の防止や犯罪の抑止、あるいは事件解決の手がかりなどにつながるわけですが、結果として私たち国民の利益が守られることになるのです。
今度は、古物商許可を申請・取得する側からみてみます。
古物商許可は一定の要件を満たした者に許可が与えられることになっています。
要件は人的要件と物的要件によって審査され、それに適合することで古物商を営んでもよいというお墨付きが与えられることになります。
その反面、古物商許可を受けた業者にはいろいろな義務が課されることになり、法令違反を行った場合、罰則や行政処分を受けることになります。古物営業を許可を受けずに行う「無許可営業」も処罰の対象となります。
このように古物商を適切に営むことができるかを営業開始前に審査し、許可を受けた者だけが営業できるようにして義務を課すことで、一般消費者が不測の損害・被害を受けることを防ぎ、あるいは犯罪の防止が図られることになります。
これもまた国民の利益を保護することが古物商許可によって実現されます。
古物商許可が必要なケースと不要なケース
「古物商」とは、古物を自ら、又は他人の委託を受けて売買等を行う営業のことです。
これだと抽象的で分かりづらいと思いますので、具体的な事例から古物商許可が必要なのか、不要なのかを確認していきましょう。
| ▼古物商許可が必要▼ | ▼古物商許可が不要▼ |
| 古物を買い取って売る | 自分で使うために買った物を売る ※未使用の物も含む |
| 古物を買い取って修理等して売る | 自分で購入した物をオークションサイトに出品する |
| 古物を買い取って使える部品等を売る | 無償でもらった物を売る |
| 古物を買い取らないで、売った後に手数料を貰う(委託売買) | 相手から手数料等を取って回収した物を売る |
| 古物を別の物と交換する | 自分が売った相手から売った物を買い戻す |
| 古物を買い取ってレンタルする | 自分が海外で買ってきたものを売る。 ※他の輸入業者が輸入したものを日本国内で買い取って売る場合は古物商の許可が必要。国内の被害品が混在する恐れがあるため |
| 国内で買った古物を国外に輸出して売る | |
| 以上の物をインターネット上で行う |
古物商許可の取扱品目(13種類)
古物の品目は13種類に区分されています。
取り扱う物によっては、どの品目に該当するのか分かりにくいものもあると思います。古物営業法施行規則等を参考に品目ごとの例を記載していますので参考にされて下さい。
| 区分 | 古物例 |
| 美術品類 | 絵画、書画、工芸品、彫刻、日本刀など |
| 衣類 | 洋服、和服、帽子、布団、その他の衣料品など |
| 時計・宝飾品類 | 時計、眼鏡、宝石類、貴金属類、装身具類など |
| 自動車 | 自動車本体、タイヤ、その他の自動車パーツなど |
| 自動二輪車・原動機付自転車(原付) | バイク本体、原付本体、タイヤ、その他のバイクパーツなど |
| 自転車類 | 自転車本体、その他の自転車パーツなど |
| 写真機類 | カメラ、光学機器、ビデオカメラ、レンズ、望遠鏡、双眼鏡など |
| 事務機器類 | パソコン、ワープロ、コピー機FAX、レジスター、計算機、シュレッダーなど |
| 機械工具類 | 電化製品、電話機、ゲーム機本体、工作機械、土木機械、化学機械、工具など |
| 道具類 | 家具、CD・DVD、楽器、ゲームソフト、トレーディングカード、おもちゃ、雑貨、じゅう器、運動用具など |
| 皮革・ゴム製品類 | カバン、靴、毛皮類など |
| 書籍 | 漫画、雑誌、文庫など |
| 金券類 | 商品券、乗車券、航空券、郵便切手、収入印紙、ビール券など |
古物商許可を取得するための要件等

要件等を満たさなければ、古物商許可を受けることができません。要件を満たしているか、以下の3点を事前に確認しておきましょう。
- 主たる営業所を設けること
- 営業所ごとに常勤の管理者を置くこと
- 欠格事由に該当しないこと(申請者本人・法人役員・管理者)
古物商許可の申請先
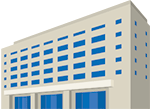
営業所の所在地を管轄する警察署を経由して都道府県公安委員会に対して許可申請します。
提出窓口は、営業所の所在地を管轄する警察署の防犯係が窓口です。
営業所を複数設置する場合は、主たる営業所を決めた上で、その主たる営業所を管轄する警察署へ申請します。
複数の都道府県にまたがる形で営業所を複数設置する場合も、主たる営業所を決めた上で、その主たる営業所を管轄する警察署へ申請します。
なお、古物商許可の取得後に営業所を新設(追加)する場合は、主たる営業所を管轄する警察署に対して、新設する3日前までに営業所の新設に伴う「変更届出書」を提出し、さらに新設した日から14日以内に管理者の選任に伴う「変更届出・書換申請書」(管理者の選任は許可証の書き換えがないため、手数料は無料)を提出する必要があります。
少し分かりにくいですが、今回のケースでは、
「変更届出書」は、追加することを事前にお知らせするための手続きで、「変更届出・書換申請書」は、許可の内容に変更があったことをお知らせするための手続きになります。これらは別々の手続きなのでご注意下さい。
別の都道府県に営業所を設ける場合
主たる営業所で許可を受ければ、主たる営業所は別の都道府県に営業所を設ける場合でも主たる営業所を管轄する警察署に事前に「変更届出書」、事後に「変更届出・書換申請書」を提出することで営業所を置くことができます。
令和2年3月31日以前は、都道府県単位の許可でしたので、別の都道府県に営業所を置く場合、当該都道府県でも古物商許可を取得必要がありました。
しかし、古物営業法の改正により令和2年4月1日以降は全国共通の許可となり、上述の通り主たる営業所を管轄する警察署に変更届出書等を提出するだけで済むようになりました。
手続きが簡便になり、変更届出には手数料もかかりませんので(※)、多店舗展開、全国展開がしやすくなったと言えます。
(※)以前は、都道府県ごとに19,000円の申請手数料がかかっていましたが、それが必要なくなりました。
古物商許可の申請に必要な書類

古物商許可の取得に際して以下の申請書等が必要となります。
申請書は管轄の警察署に受け取りに行く方法と福岡県の警察署のホームページからダウンロードするできます。
慣れないと時間はかかりますが、時間が十分に取れる場合は、ご自身で手続きするものよいでしょう。
提出窓口は、営業所の所在地を管轄する警察署の防犯係です。
表の内容は横にスワイプすると全て見ることができます。
| 申請書等 | 注釈 | |
| 別記様式第1号 その1(ア) その1(イ) その2 その3 その4 |
古物商許可申請書 | |
| 添付書類 | 誓約書 |
代表者、役員、営業者、管理者について必要。 代表者や役員、営業者が管理者を兼ねる場合でも、誓約書の内容が「個人用または法人役員用」と「管理者用」で少し異なるため、それぞれに誓約する必要があります(=同一人でも代表者として1部、管理者として1部の計2部必要)。 |
| 添付書類 | 略歴書 | 代表者、役員、営業者、管理者について必要。 代表者や役員、営業者が管理者を兼ねる場合は1部で足ります。 |
| 添付書類 | 身分証明書 (市町村が発行) |
代表者、役員、営業者、管理者が成年被後見人・被保佐人等に該当しないこと、および破産者で復権を得ない者に該当しないことを証明する書面です。 代表者や役員、営業者が管理者を兼ねる場合は1部で足ります。 |
| 添付書類 | 住民票の写し (本籍記載のもの) |
代表者、役員、営業者、管理者について必要。 代表者や役員、営業者が管理者を兼ねる場合は1部で足ります。 |
| 添付書類 | 定款謄本 (本籍記載のもの) |
法人のみ提出 目的欄に、古物商として営業することが分かる記載が必要。 |
| 添付書類 | 法人の登記事項証明書 | 法人のみ提出 目的欄に、古物商として営業することが分かる記載が必要。 |
| 添付書類 | URLの使用権限疎明資料 | ホームページを開設して、インターネットで古物を売買する場合のみ提出 開設する場合、(1)(2)いずれかの資料が必要です。 (1)プロバイダ、レジストラ(ドメイン販売業者)等からのドメイン割当通知書等の写し(「郵送」か「FAX送信されたもの」に限られます) (2)上記通知書等が手に入らない場合は、ドメインを「WHOIS検索」した際に表示される結果画面を印刷したもの。 (1)(2)のいずれも、ドメインが自身の名前、法人名、法人の代表者名で登録されていることが必要です。 ドメインの登録者名が本人と異なる場合は、URL使用承諾書が必要になります。 独自ドメイン以外の場合は(Amazon、ヤフオクショップ、メルカリショップ、eBay等)、申請者の氏名・名称、届出URL等が記載された審査完了メール等が必要となります。 |
| 添付書類 | 事務所・店舗の賃貸借契約書および使用承諾書 ※現在は不要となっていますが、警察署によっては提出のお願いをされる場合があります。 |
賃貸物件で営業を行う場合に提出 自己所有マンションの場合、管理規約で「専ら住居として使用する」などとされている場合、使用承諾書を提出 |
古物商の許可申請から取得までの期間

古物商許可の申請をした日の翌日から起算して、許可・不許可の結果が出るまで40日程度が標準処理期間(審査期間)とされています。
この期間は、いわゆる営業日で計算されますので、土日祝祭日・年末年始は除いた期間となります。したがって、実質的な期間としては40日を超えることになります。
ただ、標準処理期間は目安ですので前後することがあります。状況によっては早い場合もありますので、開店時期を判断したり、開店計画する際の一定の目安とお考えください。
書類の不備等により補正を求められたら、審査期間が伸びることになります。少し横道にそれますが、申請書提出時に補正を求められ、その場で訂正する場合は、訂正印が必要になることがあります。そのため、提出の際は申請書に捺印した印鑑も持参した方がよいでしょう。
ご依頼から取得までに要する期間
申請書作成や各種証明書の取得に3週間前後かかります。
したがいまして、申請準備期間2週間前後(14日)+審査期間40日がご依頼から取得までに要する期間となります。
ただし、審査期間には土日祝日・年末年始が含まれませんから、それらを含めると実質的には50日程度が想定されます。
これを合計すると、14日+50日で64日、およそ2ヶ月とお考えいただければと思います。もっとも、審査が早い場合もありますので、ご依頼から2ヶ月以内に許可が下りることも十分に考えられます。
古物商の営業開始後に必要な届出

古物商許可を取得した後は、一定の変更が生じた際に「変更届出書」や「変更届出・書換申請書」の提出が必要です。
例えば、営業所の新設、個人許可者の氏名変更、主たる取扱い品目の変更、古物の取引を行うホームページ等を開設など、変更事項に該当する変更がある、又は変更があった場合に変更届等を提出する必要があります。
紛らわしいですが、「変更届出書」と「変更届出・書換申請書」は、別々の種類ですのでご注意下さい。
なお、古物商許可に更新はありませんので、一定期間ごとに決まった手続きをする必要はありません。
古物商許可の申請手続き料金
基本料金は弊事務所の代行報酬、申請費用は法定の費用(ご自身で申請しても必ずかかる費用)です。それらを合計した金額がお支払い金額になります。
福岡市・春日市・那珂川市・大野城市・糟屋郡・太宰府市・筑紫野市については、交通費は無料とさせていただいておりますので、下記以上の費用はかかりません。郵送費用については、全国無料で対応しております。
表の内容は横にスワイプすると全て見ることができます。
| 申請種別 | 基本料金(税込) | 申請費用(手数料) |
| (個人様)申請代行 | 36,300円 | 19,000円 |
| 合計 55,300円 | ||
| (法人様)申請代行 | 46,200円 | 19,000円 |
| 合計 65,200円(役員1名の場合) ※役員2名以上の場合は1名追加につき2,200円加算となります。 |
||
| 各種変更届(許可取得後に変更があったときの手続き) | ||
|
【変更届出】
●営業所の移転(※)
●営業所の新設(※) ●営業所の名称変更(※) ●営業所の廃止(※) ●役員の変更(代表者以外) ●役員の住所変更(代表者以外) ●営業所等の管理者変更 ●営業所等の管理者住所変更 ●主たる取扱品目の変更 ●営業所の取扱品目変更 ●古物の取引を行うホームページ開設 ●ホームページURLの変更 ●ホームページURLの削除 |
各変更につき 11,000円 |
届出手数料:無料 |
| 合計11,000円 | ||
|
【書換申請】
●個人許可者の氏名変更
●個人許可者の住所変更 ●法人の名称変更 ●法人の所在地変更 ●法人の代表者変更 ●法人代表者の氏名変更 ●法人代表者の住所変更 ●行商「する」「しない」の変更 |
各変更につき 15,400円 |
申請手数料:1,500円 |
| 合計16,900円 | ||
※各種証明書取得 (住民票 、法人登記事項証明書 、身分証明書等)に対する手数料は、実費として別途ご請求させていただきます。
古物商許可取得~営業開始までの流れ
お客様の状況により流れは異なる場合があります。
お問い合わせ・ご相談
お電話(080-7004-7200)又はメールフォームよりお問い合わせ・ご相談下さい。
ご依頼が決まってからのご相談の場合、許可申請に必要な内容をヒアリングさせていただきます。お電話(080-7004-7200)又は申し込みフォームよりお申込み下さい。
お見積り・お申し込み
見積書をご確認いただき、ご納得いただけましたら正式にお申し込みとなります 。
警察署との打ち合わせ
警察署により必要な書類などが異なる場合がありますので、事前に申請を行う管轄の警察署と打ち合わせを行います。
申請書等作成・代行業務に着手
申請書の作成や必要種類の収集を進めて参ります。
お客様にご準備いただく書類もありますので、事前にご案内させていただきます。
警察署に申請書等を提出
作成した申請書・添付書類等を警察署に提出します。
その際、申請手数料19、000円を納付します。(福岡県の場合、県収入証紙で納付)
古物商許可証の交付
審査が終わり、許可が下りたら、古物商許可証が交付されます。お客様もしくは当事務所にて警察署で許可証を受け取ります。
【交付の際に持参するもの】
・法人代表者印(法人代表者が受け取りに行く場合)
・認印
・身分証(免許証など)
・委任状(本人以外が受け取りに行く場合)
古物商プレート(標識)の作成・購入
古物商許可証の交付を受けたら、古物商プレート(標識)を作成・購入します。
※営業を開始するには、古物商プレート(標識)を公衆の見やすい場所に掲示することが義務付けられています。
標識の主な入手方法は次の通りです。
●許可証交付の際に「古物商プレートの申し込み用紙」をもらって手続する。(受付けは古物防犯協会)
●古物防犯協会から購入
●プレート作成のネット業者から購入
営業開始
おめでとうございます。プレートを掲示して営業を開始することができます。
古物商許可申請代行申込みフォーム

古物商許可の申請代行をご依頼の場合は、お電話または申し込みフォームよりお申し込みください。営業所を福岡の対応地域に設置する場合の手続きに対応しております。ご質問やご相談は随時受け付けておりますので、ご依頼の有無に関わらずお気軽にお問い合わせ下さい。
続きを読む古物商許可を取得するための要件等

要件等を満たさなければ、古物商許可を受けることができません。要件には「主たる営業所を設けること」「営業所ごとに常勤の管理者を置くこと」「欠格事由に該当しないこと(申請者本人・法人役員・管理者)」があります。具体的な内容について確認していくことにしましょう。
続きを読む古物商の営業開始後に必要な変更届出

古物商許可を取得した後(営業開始後)は、一定の変更が生じた際に「変更届出書」や「変更届出・書換申請書」の提出が必要です。なお、古物商許可に更新はありませんので、一定期間ごとに決まった手続きをする必要はありません。
続きを読むお気軽にお問い合わせ・ご相談ください【専用窓口】080-7004-7200受付時間 8:00~19:00 [ 年中無休 ]【総合窓口】092-586-7412受付時間 10:00~19:00 [月~金]
お問い合わせはこちら まずは、お気軽にどうぞ